
彼らを保護して世話をする場合、まずはどのようにするべきでしょうか。
ここでは迷い猫・犬の保護における飼い主・里親探しについて、詳しくご説明します。
この記事が、皆様のお役に立てれば幸いです。
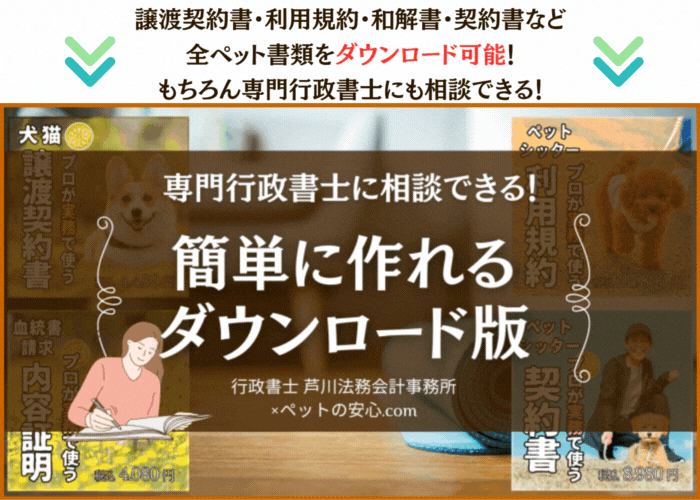
迷い猫・迷い犬の特徴と安全な保護方法
まず一般的に、飼い猫・犬には以下の特徴があります。簡素なポイントですが、まずは確認してみましょう。
- サマーカットや爪切り等、トリミングが施されている
- 犬なら鑑札・注射済票、猫なら首輪・マイクロチップなどを装着している
- 人懐っこく、手から食事を直接食べる
- 定期的なワクチン接種の形跡がある
あとは人懐こさや食事の様子です。エサを与えられていない野良猫・犬とは、明らかに接し方が異なります。
飼い猫・犬であるか確認した後は、以下の場所に迷い猫・犬を保護している旨の連絡をします。
拾得物としての届出
- 最寄りの交番、警察署に連絡する
これは飼い猫・犬だと知って届出をしなかった場合の、以下の罰則を回避するためです。
遺失物等横領(刑法第254条)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また飼い主がいない(所有物でない)猫・犬を保護した場合、以下に該当し所有権を取得できる場合が生まれます。
無主物の帰属(無主物先占)(民法第239条第1項)
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
飼い主が迷子猫・犬を遺失物として届出をしていた場合、その飼い主に連絡が取られます。
「保護できない」と申し出た場合、多くの場合、警察から保健所・動物愛護センターに送られ、飼い主・里親が見つからない場合、所定の期間経過後(即日~数日後)に殺処分されます。
次に迷い猫・犬を保護している旨の届出を行います。
保護情報としての届出
- 最寄りの保健所、動物愛護センターに連絡する
また迷い猫・犬を保健所で預かっていただいた場合も同様に、所定期間経過後に殺処分される可能性がありますのでご注意ください。
そのため警察・保健所へ連絡を行う際は、迷い猫・犬を保護している情報だけをお伝えし、自宅で飼い主・里親が見つかるまで保護すると良いでしょう。
安全で効果的な飼い主・里親の探し方
そのため迷い猫・犬の届出後、3カ月感は元の飼い主を捜し、その後は飼い主探しと並行して新しい里親を探すと良いでしょう。
勿論この場合、自身の犬として飼育する選択肢もあります。
飼い主と里親の効果的な探し方には、以下の方法があります。
飼い主と里親の効果的な探し方
- 動物愛護団体に保護猫・犬の登録を行う
- 動物病院・ペットサロンなどの里親探しを支援している場所にお願いする
- 里親募集を愛犬家などの個人ブログに掲載してもらう
- SNSなどで里親募集情報を拡散する
SNS(twitterやFacebookなど)を利用して里親を募集する方法も主流です。また、その際はハッシュタグ利用した拡散方法も効果的です。
ハッシュタグ
ハッシュタグとは、ツイッターやフェイスブックなどの発言を、カテゴリをつけて検索しやすくするために#xxx」と入れるタグのこと。イベントや興味のあるコンテンツを発言している人の検索を、より簡単にしてくれる役割を持つ。
必ず譲渡時には実際に対面し、譲渡条件や譲渡先の情報などを伺いましょう。
参照:愛犬・愛猫の安全な譲渡にむけた重要事項チェックシート
:犬・猫の譲渡の前に定める仮里親期間の効果と準備書類(条項付き)
里親を見つけやすくする対策
次に、新しい里親を見つけやすくする工夫です。
里親が引き受けやすいよう、保護主側は以下のご配慮をされると良いでしょう。
- 健康診断で猫・犬の健康状態を明確にする
- 健康診断で年齢・性別・体重など、譲渡時に大切な情報を用意する
- ワクチン接種など、里親が引き取りやすい環境を整える
- 譲渡が決まるまで室内飼育を行い、感染症やトラブルを防ぐ
また中にはワクチン接種は生体上必要ではない、という意見をお持ちの方もいますので、獣医師にワクチン接種の必要性を伺いましょう。
皆様のより安全なペットライフをお祈りしております。
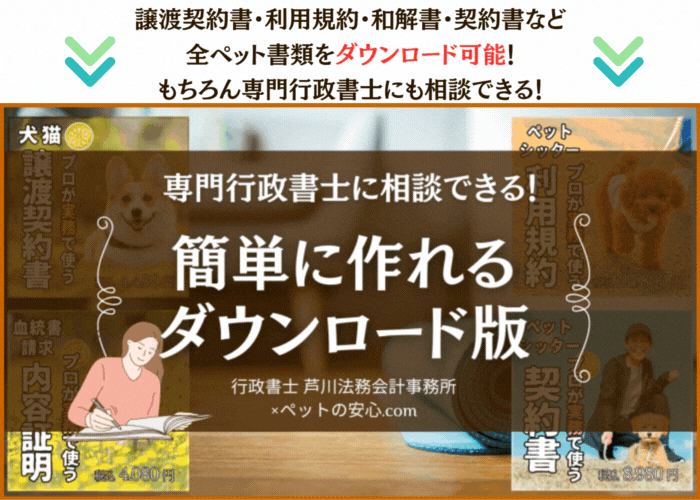
“迷い猫・犬を保護した時の効果的な飼い主・里親探しの手順” への2件のフィードバック