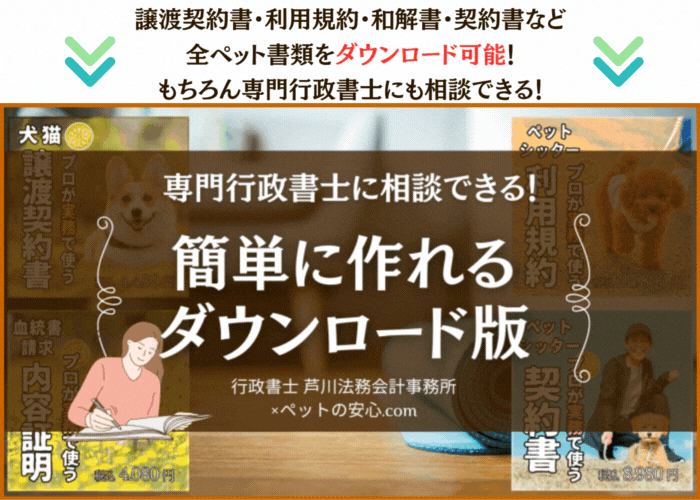元親から愛犬・愛猫を譲り受ける時、その方が非常に意見の強い方だったら。
そしてその方が以前にも、譲渡後にペットの返還を請求していたら。
ここでは元親の過干渉を回避するペットの譲り受け方法について、詳しくご説明します。
この記事が、より良いペットライフに繋がれば幸いです。
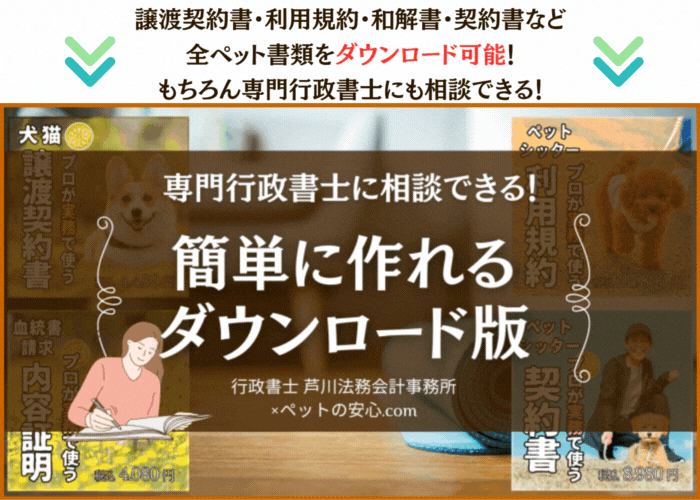
元親の過干渉が危惧されるケース
元親の過干渉には、譲渡後も里親の飼育方法や飼育環境などに対する意見を過剰に伝え、時に譲渡ペットの返還を請求する場合があります。
その多くは元親としてペットを大切に飼育して欲しいと思う気持ちによりますが、あまりに干渉が強すぎる場合、里親側のペットライフに支障をきたしかねません。
過干渉が危惧されるケースには、以下の点が多く見られます。
- 1. 過去に譲渡後に返還を請求していることがある
- 2. ペットに対する愛情があまりに強い
- 3. 口約束で譲渡し、明確に所有権を譲渡していない
- 4. 保護団体などの思想・理念が強く反映されている
- 5. 譲渡時に過度に細かな飼育条件を指定される
勿論、これらに当てはまると必ずしも過干渉に繋がるということではなく、あくまでも経験上・体感的なものです。
そして実際に過干渉に繋がるかどうかは、ご自身で判断しなければなりません。
実際に元親とお話をして、「過干渉の恐れがある」とご自身で判断された場合、譲渡時に将来的な過干渉を抑える方法を検討すると良いでしょう。
具体的な予防方法
具体的に過干渉を予防する方法には、以下の例があります。
- 飼育方法は里親が全て決定する譲渡条件にする
- ワクチン接種なども全て里親が行い、報告義務を設定しない
- 譲渡契約書を締結し、所有権の移転を明確にする
- 譲渡後の連絡は定期連絡を設定し、それ以外は連絡をしない取り決めをする
- 譲渡時に第三者を招き、正式な譲渡である旨を印象づける
これらの配慮により、「この様に飼育したほうが良い」「譲渡条件に相違しているので返還して欲しい」といった意見や請求を防ぐことができます。
そして元親様からの強い意見に対しても「里親である私が責任を持って飼育します」と強く提示できます。
また正式に譲り受けている証拠としての譲渡書類がありますので、譲渡条件の違反がなければ返還の請求も難しくなります。
最も問題となるケースは口約束で譲渡をしている場合です。「大切に飼育してね」という約束をしている場合、様々な角度から飼育方法や飼育環境の改善を求める理由と成り得ます。
それが過度な干渉に繋がり、同時にそれを拒否しづらい状態が完成してしまいます。「約束したじゃない!」といつまでも干渉が続くケースも少なくないでしょう。
これらをまとめると、譲渡時に以下の意識を持つことが大切です。
- 飼育方法は里親が全て決定すること
- 返還を求められないよう、所有権を明確に譲り受けること
- 干渉を強く断れる根拠を用意しておくこと
- 第三者から見ても、正式な譲渡が完了していること
ただ、提案の前提として相手の出方に応じた、より平穏な提案方法をご検討ください。
「過干渉の心配があるから設定したい」と相手に直接伝わらないよう、相手の気持ちを尊重した提案方法が大切です。
と言うのも、過干渉はあくまでも「元親のペットに対する愛情」から生まれるものが多く、一概に問題のある行為とも言い切れないためです。
過干渉であることで自身のペットライフを守る側面と、ペット仲間となるであろう元親様との関係に配慮した選択が必要です。